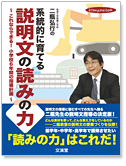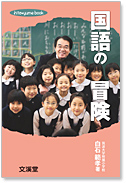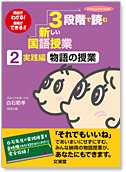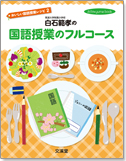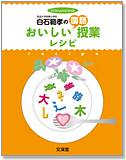国語科 主体的学習における教師の「指導」
-学習のための指導・学習のための評価-
勝見 健史(著)
主体的な学びを実現するカギ「11の指導」を大公開!
「主体的な学習」とは、決して教えることを放棄して子どもに活動を放任したり、見通しを持たず子どもの後追いをしたりすることではありません。
これからの授業における「内容を教える」を越えた教師の役割、「学習のための評価」「学習としての評価」のための教師の立ち位置についてわかりやすく解説しています。
「主体的な学習」を授業実践で具体化していくためのたくさんのヒントが書かれている現場の先生方に必携の書です。